作家の司馬遼太郎さん(平成8年 1996年死去)が主に環境問題について公演したものが、「十六の話」という司馬遼太郎さんのエッセイ集に収録されています。
調査不足でこの公演自体がいつ頃されたものなのかわかりませんが、地球の未来について訴えかけているものです。
ふと、司馬遼太郎さんがSNSの発達した「現在」を見た時に、「訴える相手」がいると考えるのか。と思いたち記事にしています。
マーク・トウェインの作品から見るアメリカ精神史の一片
このエッセイの冒頭部分でマーク・トウェイン(アメリカ作家、作品は「トムソーヤの冒険」「人間とは何か」など)の書籍からアメリカの精神史・もしくは19世紀後半から20世紀初頭までの科学技術に関する考え方について解説しています。
マーク・トウェインは19世紀後半までは「進歩ほどすばらしいものはない」という非常に明るい思想のもと多くの作品を生み出し続けました。
ですが、晩年は世界や人間に何の希望も持たない思想家になっていました。
その思想とは大きく2つであり、
- 人間にはひとかけらも崇高さなどない。「自己犠牲」なども他人のために行うことはない。自分を満足させるために行っている。例えば一駅移動をしたいとき、電車賃のない老人がいたとする。その老人に電車賃を渡し、自分は歩いて帰ったとしても、それば僅か数百円で心地よい・良いことをしたという満足感と得たに過ぎない。
- 人間だけに備わった創造能力なども嘘っぱちだ。過去の知識のうえにもう一つ知識を積み上げただけであり、猫やネズミも経験を重ねればそれなりの規模で何事かをするだろう。人間の崇高さの証明にはなりはしない。
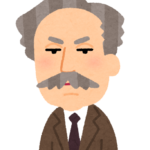
人間には素晴らしさなど一つもない。
自己犠牲は自分のため。
創造能力も真似を重ねただけで大したこと無い
この思想は当時の一般的な思想とはかけ離れており、敬虔なクリスチャンであったマーク・トウェインの妻は、この原稿を読み、気を失いそうになったそうです。
そのように当時の人々には衝撃的な内容の思想であっても、アジア人にとっては、実はそう珍しい思想ではありませんでした。仏教の思想により近いものであるということです。
「うしなう」ことと「捨てる」こと
司馬遼太郎さんは、「うしなう」ことが、結構気楽であることをお話しています。
日本は、富国強兵のもと前進していましたが、その思想を捨てざるを得なかったとき、ほんの僅かな間だけ、太古の昔、狩猟採取の生活をしていたころのような気楽さになり「うしなった」わりには体の中から哄笑が湧き上がったようです。

強兵は別にして、富国は今でも変わりませんし、
世界各国が目指していますね。
また、「捨てる」ということについてです。
十三世紀ごろ仏教は「日本化」していき、「捨てる」ということがテーマとなっていったとのことです。なにかに対する執着を捨てることで自由になる、苦しみから開放される。「苦しみから開放されたい」「悟りを開きたい」という思いすら「捨てる」ことが重要と説かれています。
この「捨てる」という思想は日本人に意識するとしないとを問わず、影響を与えている思想だと思われるようです。
マーク・トウェインはまだ幸せだった
マーク・トウェインは二十世紀前半に絶望的な思想を持つに至りましたが、かれはそれでも幸運だったとのことです。
なぜなら「だから地球はほろびる」とまで考えが飛躍するような世界ではなかったからです。
現在の人々はその崇高(?)な「創造能力」によって巨大な力を手に入れました。それは地球の滅亡を容易に想像できる力で、主に兵器類と巨大な土木技術です。
この巨大な力は厳密には国家が持ちました。その国家は所属する国民を守るために利己的な行動をします。国家は人間と同じように自己犠牲などは行わない。ということです。
訴える相手がない
司馬遼太郎さんは子孫に残すものは「地球」と答えています。
正確には、人間がその生命を保ち続ける生態系をもった地球です。
ですが、この利己的な国家がひしめくなかでは、「ひとびと」のレベルで共通の目的をもって解決されない限り、われわれの子孫は壊れた地球しか相続できないとのことです。
ですが、その「ひとびと」は百万人単位で行わなければ、真に力のある「ひとびと」にはならない。それは今世紀(20世紀)では近代国家群とイデオロギーが邪魔をして実現不可能な難題とのことです。

また、利己的な国家群は創造能力で巨大な力を手に入れましたが、もう一つの地球を作ることができない限り、この巨大な力は「誇る」ことができず、未来のために「抑制」されるべきとのことです。
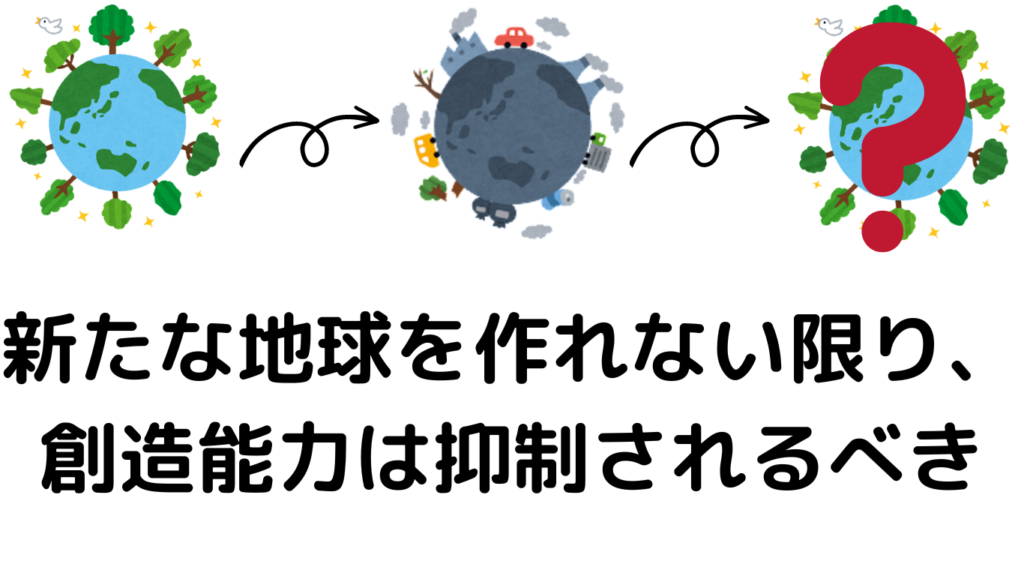
ですが、「今日と明日のパン」を追い求める国家や企業にとって、「百年先のパン」は架空のものになり、国家や企業が「抑制」をすることはない。また、20世紀において百万人単位の力のある「ひとびと」はいない中でこのように語っています。
この世に、国家やイデオロギーを超えた存在で、しかもそれらに影響をあたえうる「無名の、しかも良識のある多数の個人群(ひとびと)」など存在するはずがなく、従って私は居もしない相手に向かって訴えようとしているのです。しかし過去において存在しなかったといっても、将来、百年後に、ひょっとすると出現するかもしれません。そういうかぼそい可能性にむかってしか訴えることができません。
訴える相手がないまま
としてこのエッセイは終わっています。
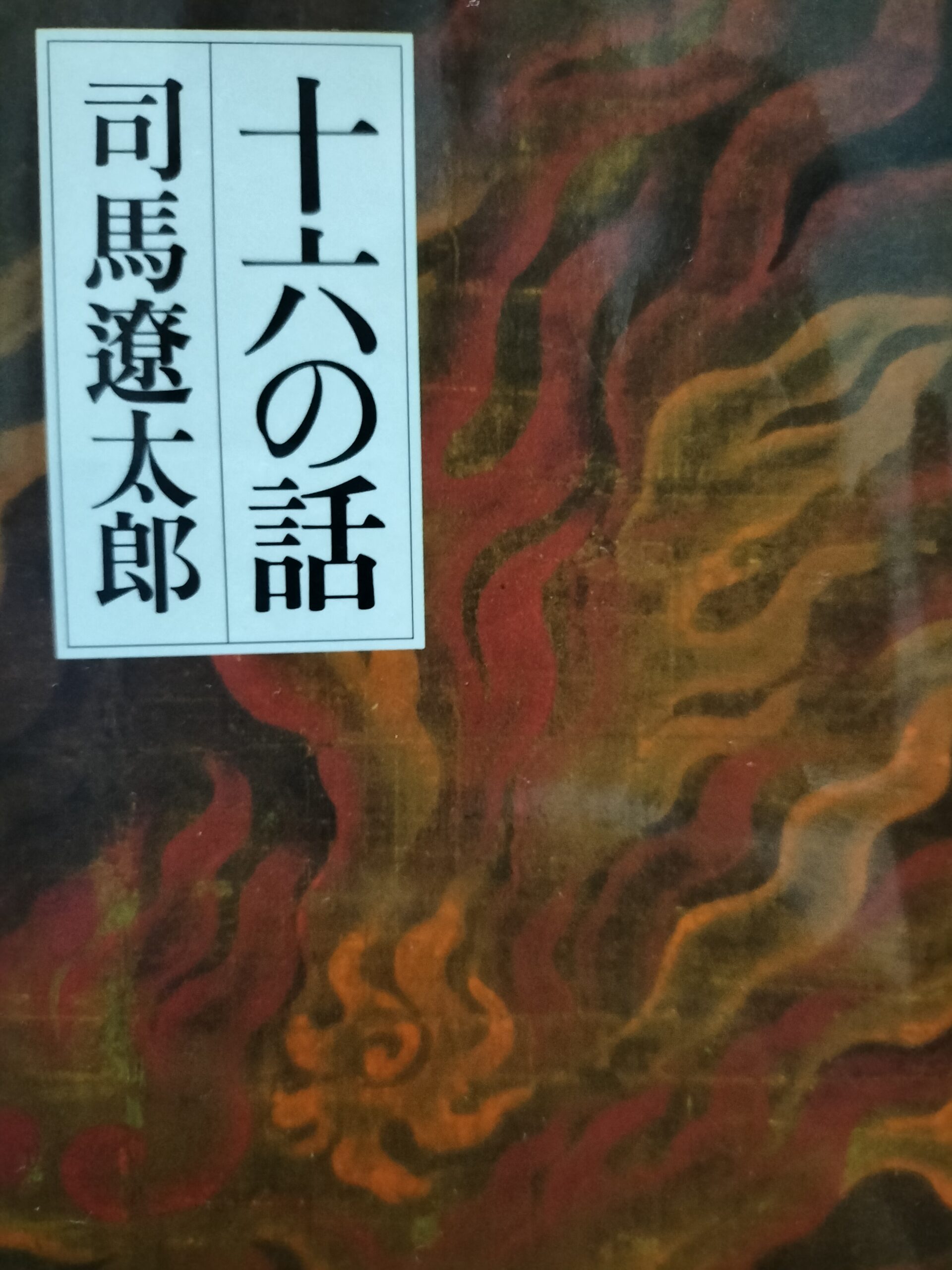


コメント